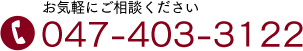津田沼不動産相談センターのご提案
第2の人生設計をサポートいたします。
不動産相続の手続き
不動産の所有者が亡くなったら、不動産の名義を変更するために、相続登記をしなければなりません。
手続きがわからない・手間を省きたいなど様々なお考えがあるなら津田沼不動産相談センターに依頼するのがオススメです。
相談することで不動産手続きはもちろん、その後の遺産分配方法などにもご対応いたします。
相続登記手続きに関して、津田沼不動産相続相談窓口に依頼すれば、不動産が遠方にある場合でも手続きを進められます。
相続登記は、オンライン申請に対応していることが多いため、全国各地に不動産がある場合でも問題なく手続きができます。
不動産の相続登記が必要になった場合には、津田沼不動産相談センターにご相談ください。
津田沼不動産相談センターでは、司法書士の国家資格をもった登記手続きの専門家がいますので、安心して相続登記を任せられます。
面倒な手続きはすべて司法書士が代行いたしますので、スピーディーかつスムーズに相続手続きが完了します。
不動産相続の実費

相続による不動産名義変更の実費は大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。
「登録免許税+その他(戸籍等費用および送料等)」
●「登録免許税」
法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
相続の場合には固定資産評価額の0.4%が納税額になります。
例えば、不動産評価額が1,000万円であれば4万円です。
●「その他(戸籍等費用および送料等)」
戸籍謄本等の費用
・戸籍謄本 450円
・除籍謄本 750円
・改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
・不在住証明書 300円
・不在籍証明書 300円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。
登記事項証明書(登記簿謄本)
1通600円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通335円です。
郵送料
戸籍等の郵送請求や登記申請の際に必要になります。
請求する戸籍の通数等によって変わりますが数千円くらいのイメージです。
不動産相続節税対策
不動産を相続した場合には、相続税といわれる税金がかかる場合があります。
但し、不動産を相続したすべての方にかかるわけではなく、相続税がかかるのは統計上、全体の約5%程度の人のみとなります。
相続税は、「被相続人の相続財産のすべての合計額」が「基礎控除額」を超える場合にかかってきます。
あなたが相続した不動産の価値だけではなく、他に相続した金融資産や、他の相続人が相続したものをすべて含めなければ、相続税がかかるかかからないかの判断はできないこととなります。
同じ価値の相続財産でも、相続する資産の内容により相続税の金額は異なります。具体的には、現預金で相続するよりも不動産で相続する方が相続税が大幅に節税できることになります。
例えば、1億円の現預金が相続財産としてあった場合、相続税評価はそのまま1億円となり、仮に相続税の税率が50%の場合は、5,000万円の相続税がかかります。
しかし、1億円の現預金で1億円の不動産を購入した場合、物件の種類にもよりますが、相続税評価は7,000万円程度になります。その場合、税率が50%でも相続税は3,500万円となり、先ほどの場合と比べると1,500万円も節税になっていることが分かります。
不動産を活用した相続税対策は、節税効果が大きい反面、投資額も大きくなりますので相続税の節税だけにとらわれずに実施の有無を検討する必要があります。
津田沼不動産相談センターでは不動産を活用した様々な相続税対策にご対応いたしますのでまずはご相談下さい。
相続・税金について

相続税とは、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金のことです。
亡くなった人を被相続人とよび、相続によって財産を受け継いだ人を相続人とよびます。
相続の流れ
①被相続人が亡くなる
②遺言書があるか確認する
③相続人を確定する
④相続財産を調査する
⑤単純・限定承認/相続放棄の手続き
⑥遺産分割協議を行う
⑦遺産の分配・名義変更を行う
⑧相続税の申告・納付
天井が高い部屋は開放感がありますが、冬は寒く、暖房費がかかりやすくなります。
見学する時期だけでなく、一年を通して快適に生活できるか確認しておきましょう。
また、相続税がかかる場合、以下の3種類のケースがあります。
-
相続
亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”決めていなかった”ものをいいます。最も多いケースですので、多くの人がこれにあたります。
-
遺贈
亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”遺言(いごん、またはゆいごん)で決めていた”ものをいいます。近年増えてきたケースです。 簡単にいうと、相続人が財産をもらえる事実を知らないで一方的に財産を与えるのが遺贈です。
-
死因贈与
亡くなった人が生前に自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”契約で決めていた”ものをいい、これを「死因贈与」といいます。 遺贈と違う点は財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけではなく、財産をもらう人も「財産をもらいます」と表明しているところです。
-
生前贈与
被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等(誰でもよい)に財産を渡すことをいいます。 特定の人(誰でもよい)に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。
お金の有効活用について

まず一つに、家のローンが残っている場合、退職金で返済するという方法があります。社会保険庁から送られてきた「年金定期便」で、自分が受け取れる年金のおおよその額がわかるので、家計に余裕があるようなら、退職金で全額を完済してしまうのもいいでしょう。
また、退職金で今の家を改築して一部を貸したり、家ごと貸して自分たちはライフスタイルに合った別の物件に引越しをするという方法もあります。
一部を貸した場合、毎月の家賃が得られます。家ごと貸した場合でも、引っ越した物件よりも高い金額で家賃を設定できれば、その差益は収入となります。
「減築」をして、空いたスペースを駐車場として貸す方法もあります。いずれも副収入として有効な活用方法です。
資産運用として不動産投資するのもよいでしょう。ワンルームマンションを購入し、学生や独身者に貸して毎月の家賃収入を得る、いわゆる大家さんになることも一つの方法です。
定年後の生活を考える
定年は思っている以上にあっという間にやってきます。いまから簡単な未来予想図を考えておきましょう。
5年刻みくらいのスパンで、自分や家族がどうなっているか、ざっくりとでもシミュレーションをしてみると、現実感が出てきます。
定年を迎えると、次に掲げる事例のように、それまでとは生活環境が大きく変わります。
これらの変化への対応は一朝一夕にはできません。
今から様々な変化を想定し、家族、特に配偶者と相談してそれらへの対応を考えておくことが大切です。
自分や家族の健康状況
現役時代は当たり前だった健康な身体。だが定年後は、しっかりとした健康維持管理を行いましょう。
何をするにも、あなたの活動を支えるのはあなたの身体です。
家族の生活状況(配偶者の就業、子供の自立、両親の介護など)
家計や住居の状況(月々の収支、ローンの返済、修繕費の必要性等)
年金が支給されても、定年前に比べると収入は大幅に減ります。
定年後の収支を想定し総合的に判断しましょう。
趣味、やりたいこと
定年後は、通常、拘束されない時間が大幅に増えることになります。
やりたい事をやる,それが生き生きした定年後の人生だと思います。
セカンドライフのタイミング

現在、一戸建てにお住まいの方の不安や悩みは、建物の維持管理を負担とされている方が多くみられます。
また、一戸建ての場合、中心部から離れた立地に位置する場合が多く、「車が不可欠な場所では老後の買い物・通院が不安」という声が多数です。
また、「夫婦2人暮らし」のニーズが高まっているのも近年のセカンドライフの特徴。
子供家族との同居より、夫婦2人で気兼ねなく暮らしたい。
「第2の人生」を自分の為に楽しもうとされる方が多い様です。駅に遠くメンテナンスに負担がかかる一戸建てより、コンパクトで利便性の高いマンションなどを終の棲家とする傾向は、今後ますます強くなると思われます。
どこに住みたいか考える

定年後の生活設計を考えるうえで「どこに住むか」ということがポイントになってくるかと思います。
公務員宿舎や社宅住まいであれば、新たな住居を探さなければなりません。
すでに住む家があっても、退職による生活パターンの変化や、
子供が独立して親元を離れることなどを契機に引越しを考える方もいらっしゃるでしょう。
最近、定年後は地方でのんびりと暮らしたい、気候が温暖で物価が安い海外に、移住や長期滞在したいという方が増えているようです。
しかし、住み慣れた地域を離れて、他の地方や、さらには外国に住む場合は、これまでとは異なる環境において生活することになるわけですから、事前によく調べ、まずは短期間暮らしてみるなど慎重に考えていきましょう。
退職後の住居を考える際の一つのポイントは、何を生活の中心とするかです。
在職中には、仕事が生活の中心であった方も多いと思いますが、退職後は、どのような活動が中心になるでしょうか。
家族と一緒に過ごす時間、趣味、ボランティア活動など、様々だと思います。そうした活動に適しているのは、都会でしょうか、地方でしょうか、また一戸建でしょうか、マンションでしょうか・・・・。
これからの生活をイメージして、一つ一つ考えていきましょう。
セカンドライフの住まい選択

シニア世代の住まいの選択肢にはどのようなものがあるのでしょうか。
自宅のリフォーム
段差をなくしたり(バリアフリー)、手すりをつける、浴室に滑り止めをつける、ヒートショック対策を行うなど長年住み慣れた家を快適にリフォームし、自宅に住み続けるという選択肢があります。
※ヒートショック対策は、寒い時期に、部屋の温度差によって引き起こされる脳卒中や心筋梗塞を防ぐリフォームです。
マンションへの住み替え
年をとるにつれて、室内の段差やお風呂・トイレなどの気温差に敏感になってきます。最近のマンションでは、最初からバリアフリーになっていたり、トイレや廊下などに手すりが付いていたりと、親切な設計になっているところが増えています。
そこで、一戸建てから便利で住みやすいマンションへ住み替える方が増えています。
一戸建てよりも戸締りが楽ですし、維持管理が手軽で、段差も少なく、セキュリティに優れているなどのメリットがあります。
二世帯住宅
親子世帯が一緒に暮らす住宅形式です。土地の有効活用が図れ、資金面も建設費だけでなく公共料金や光熱費なども分担できるという経済的メリットがあります。
それ以上に親族がすぐ側にいることの安心感や安らぎを感じられ、子育てや介護などをお互いに助け合えるという精神的なメリットが大きいようです。
高齢者住宅(シニア向けマンション)
駅に近く、緑が多い、など高齢者のご希望に合わせた分譲または賃貸マンションです。
自立した生活ができる高齢者が対象となっています。
他にも、入居希望者が集まって建設組合をつくり、共同でマンションの建設を進めるコーポラティブハウスや、自然に囲まれてのびのびと暮す田舎暮らしや、海外に住居を構え暮らす海外移住などがあります。
安心した生活を始められるよう、どの暮らしがご希望なのか、ご家族とよく相談しましょう。
住み替えとリフォームの選択

ライフスタイルや同居人数が変化した際、リフォームするか住み替えをするかで悩まれる方が多くいらっしゃいます。
リフォームと住み替えのそれぞれのメリット、デメリットを挙げてゆきましょう。
■リフォームをする場合
- メリット
- ・建物を壊さずに済む。
・大規模なでなければ、ほとんど仮住まいや引越しがいらない。
・予算に合わせたリフォームができる。
・内外装とも新築同様にすることができる。
- デメリット
- ・建物の構造によっては、間取り変更などが思い通りにならない場合がある。
・基礎、柱、梁などの主要な部分を補強しない場合、構造の強度に不安が残る。
・構造補強を含めると、建替えより高額になることがある。
■住み替えをする場合
- メリット
- ・売却益を住み替え資金にする場合、自己資金を用意する必要がない。
・売却益が、住み替え予算より多ければ、老後の資金等に充当できる。
・マンション購入、一戸建て購入、土地を購入して建物新築、賃貸など選択肢が広がる。
・オーバースペック(過剰)な住まいから適正な住まいに変更できる。
(敷地が広すぎて、庭の手入れなどができない。不使用の部屋があり、掃除が面倒など)
- デメリット
- ・長年暮らした愛着のある土地、建物を手離さなければならない。
・マイホームを売却しても、利益が出ない、または、マイナスが発生することがある。
(住宅ローンの残高が高額な場合、売却時補てんしなければならないこともあります)
・マイホームの売却を初めに行った場合、思い通りの金額で売却できても、理想とする住まいが見つかるとは限らない。
・住み替え後の住まいの購入を初めに行った場合、売却期間が思うようにとれず、思い通りの金額で売却できない可能性がある。
・地域、近隣など環境が変わるので気苦労をする場合がある。
住み替え時の物件選びのポイント

元気なうちに住み替えを考え、実際に動き出すことが重要です。介護が必要になってからでは、自分好みに合うところに住めないことも考えられます。住み替えには引越し、家具などの整理や処分など必要なので、気力と体力が必要となるのです。
また、将来を見据え、駅やスーパー、病院が近い場所を選ぶことが重要になってきます。
車の運転や長い距離の徒歩など若い頃より衰えを感じ不安になるものです。利便性の良い場所に住み替える選択はおすすめです。
自分たちに最適なスペースの物件を選ぶことも大切です。高齢になると階段や庭のお手入れなどが大きな負担となってきます。
広すぎると掃除が大変だったり、光熱費も余分にかかってしまったりします。
また、日中、家にいる時間が長くなってきますので、日当たりなどの住環境も重視しましょう。
住み替え時の見学のポイント

物件だけでなく、周辺環境や距離感を把握することも大切です。
見学する際には、車で見に行くだけでなく、電車やバスなどの公共交通機関を実際に利用してみて距離感をつかんでみましょう。
昼間の明るい時間に見学し、室内や日当たりを確認したり、時間帯や曜日を変えて、周辺環境をチェックしたりしてみましょう。
昼と夜、平日と休日では周辺の雰囲気が違う場合があります。
部屋に関してもよく確認しましょう。
- 配置や窓の向きと位置、大きさ
- 窓や扉は実際に開閉させて、使いやすさを確認
- 室内の段差
- 各部屋に収納スペースはあるのか、どのくらい収納できるのか
- 天井の高さや風通し
天井が高い部屋は開放感がありますが、冬は寒く、暖房費がかかりやすくなります。
見学する時期だけでなく、一年を通して快適に生活できるか確認しておきましょう。
津田沼不動産相談センターは相談無料で受け付けております。
遺産や相続の悩みや問題などしっかりご対応させていただきます。
法定相続人・土地の相続分割・税制改正後の相続税・遺産調査など以外にも、
不動産登記・保険手続き・その他相続に関わる書類作成・土地の評価額の調査など
相続に関わる事すべて相談・実施可能です。